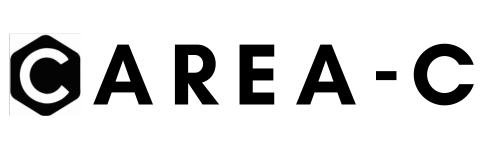開業医として経営を続ける中で、「医療法人ではできないこと」が足かせになる場面は少なくありません。たとえば、自由診療に関連する物販、家族の雇用、資産の保有や承継――これらは医療法人の非営利制により制限される項目です。
そこで注目されているのが「MS法人」です。医療行為は行わないものの、事務・資産管理・人事・周辺事業などを担う法人として、医療法人ではカバーしきれない部分を補完します。
この記事では、MS法人の基本から、医療法人との違い、メリット・デメリット、そして開業医が実際にどう活用しているのかまで、実務目線でわかりやすく解説します。
H2:MS法人とは?

MS法人(メディカル・サービス法人)とは、医療機関の経営や運営を支援するために設立される一般法人(株式会社・合同会社など)です。医療行為は行わず、周辺業務や管理業務を担う裏方の法人として活用されます。
医療法人と異なり、MS法人は会社法に基づいて設立され、医師資格も不要。利益を出すことや資産の保有、家族の雇用といった営利活動にも制限がなく、自由度の高い法人形態です。
H3:MS法人の目的
医療法人には「非営利性の原則」があり、経営的な自由度が非常に限られています。この制度は公益性を保つために設計されていますが、実際の医院経営においては、以下のような課題を生みます。
- 資産を法人名義で保有・運用できない
- 家族に給与や役員報酬を自由に設定できない
- 利益を法人外に出せない(配当不可)
- 医療以外の営利事業(物販・自由診療周辺など)が制限される
たとえば、医院の土地や建物を医療法人で所有すると、売却や相続時に制限がかかります。また、受付や事務を担当する家族に対しても、医療法人のガイドラインに則った報酬制限があります。
こうした制限を回避し、経営的に柔軟な運用を行うための「受け皿」として設立されるのがMS法人です。
MS法人は会社法に基づいて設立される一般法人であるため、次のような点で、医療法人では不可能な経営戦略を補完できます。
- 資産保有(建物・機器)や賃貸が自由
- 家族を雇用し、報酬を支払うことが可能
- 自由診療や物販などの周辺ビジネスにも対応
- 所得分散・節税・承継対策にも応用可能
つまりMS法人は、制度の「抜け道」ではなく、診療と経営を適切に切り分けるための合法的な設計です。
H3:MS法人の業務内容と実際の使われ方
MS法人は、医療行為を一切行わず、あくまで医療機関の経営・運営をサポートする法人です。主な業務内容は以下の通りです。
▷ 医療機関からの委託業務
- 医療事務(レセプト請求・予約受付・カルテ入力補助など)
- 会計・給与計算・経理代行
- 医療機器や消耗品の仕入れ、在庫管理
▷ 資産の保有・運用
- 医院の建物をMS法人が所有し、医療法人に賃貸(賃料収入)
- 医療機器をMS法人が購入し、リース契約で医療法人に提供
- ITシステム・什器などの設備管理
▷ スタッフの雇用・人事
- 医療法人で雇用できない配偶者・家族をMS法人で雇用
- 受付・事務・清掃・電話対応など医療従事者以外の人材管理
▷ 周辺ビジネスの展開
- 化粧品、健康食品などの物販
- サプリメントや美容医療関連品の提供
- 経営コンサルティングや集患マーケティング支援
こうした活用により、医療法人の制約下でも柔軟で効率的な経営体制を築くことが可能になります。
実際には、「診療は医療法人」「経営と資産管理はMS法人」という二法人制での運営が増えており、節税、経費処理、事業承継、相続対策といった多方面のニーズに応える運用方法として機能しています。
H2MS法人と医療法人との違い
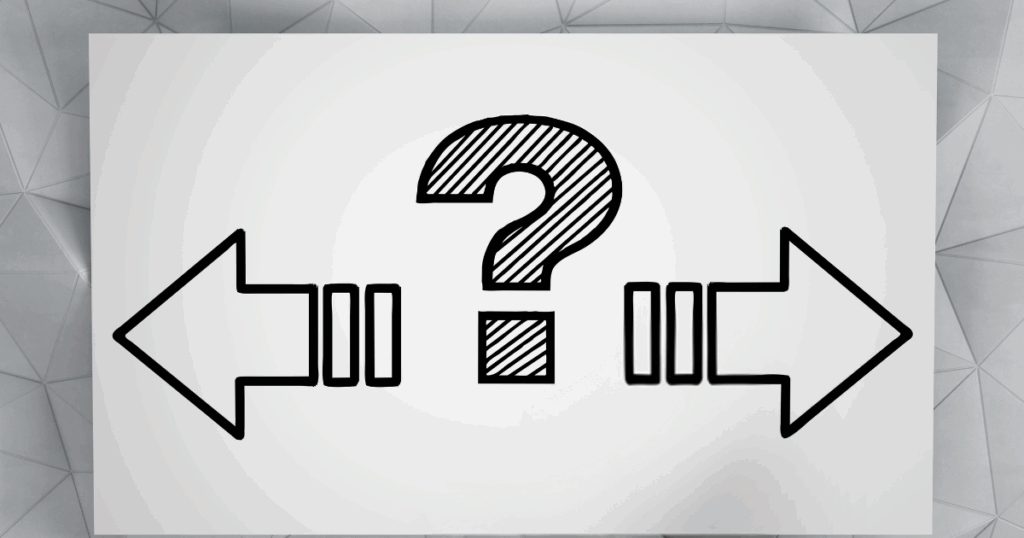
MS法人と医療法人は、名称が似ていて混同されがちですが、そもそもの制度目的も、できることも大きく異なります。特に、医療行為の可否・営利活動の自由度・設立条件・資産保有の扱いなどで明確な違いがあります。
以下は、両者の主な違いを整理した表です。
| 項目 | 医療法人 | MS法人 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 医療法 | 会社法 |
| 医療行為 | 可能 | 不可 |
| 主な目的 | 医療提供(診療・治療) | 医療機関の経営・運営支援 |
| 営利活動の可否 | 非営利 | 営利活動可 |
| 設立の要件 | 都道府県知事の認可 | 登記のみ |
| 資産の保有 | 原則制限あり | 制限なし |
| 家族の雇用・報酬 | 一部制限あり | 制限なし |
| 活用されるケース | 病院・診療所の運営主体 | 建物管理、受付・事務外注、物販、集患支援等 |
両者は対立するものではなく、役割を分けて併用することで、医療と経営のバランスを取る設計が可能になります。制度的な違いを踏まえたうえで、実際の現場ではどう使い分けられているのかを見ていきましょう。
実務上の使い分けと、分けて運用する理由
医療法人とMS法人は、それぞれの得意分野を分けて活用するのが基本です。医療法人は診療を行い、MS法人は事務・経理・資産管理など診療以外の業務を担います。
医療法人には、営利活動や資産保有、家族への報酬に制限があります。そこでMS法人を併設し、業務や資産をそちらに移すことで、制度の枠内で柔軟な経営が可能です。
たとえば以下のように使い分けます。
- 診療・保険請求 → 医療法人
- 不動産・医療機器の所有 → MS法人
- 家族の雇用・報酬支払い → MS法人
- 自由診療に関わる物販 → MS法人
このように役割を分けることで、節税や事業承継、相続対策にもつなげやすくなります。
H2:MS法人の主なメリット

MS法人は医療行為こそ行えませんが、経営・税務・資産管理の観点で開業医にとって多くのメリットがあります。
とくに医療法人では制限のある活動や、個人開業では難しい節税・資産戦略の幅を広げられる点が大きな利点です。
- 節税効果が見込める
- 資産保有・投資など医療法人では制限される活動が可能
- 柔軟な人事運用が可能
以下に、開業医がMS法人を活用することで得られる代表的なメリットを解説します。
H3:節税効果が見込める
MS法人の最大のメリットのひとつが、税務戦略の自由度が高いことです。個人で医院を経営する場合、所得税の累進課税によって高所得層では税率が最大45%に達することもあります。
これに対してMS法人を設立し、業務の一部(清掃・物品購入・受付業務など)を法人に外注することで、その支払いは医院側の経費として計上可能になります。
さらに、MS法人側で役員報酬や人件費として所得を分散すれば、税負担全体を圧縮できる可能性があります。これはいわゆる「所得分散」による節税です。
もちろん形式的なスキームでは税務上否認されるリスクがあるため、業務実態と契約の整合性は必須です。
H3:資産保有・投資など医療法人では制限される活動が可能
医療法人は、「医療を提供すること」を主たる目的としており、不動産投資・金融資産の保有・別事業への投資などに法的な制限があります。
一方、MS法人は会社法上の一般法人であるため、不動産購入・リース業・他事業展開など、幅広い経済活動が可能です。
たとえば、以下のような活用例があります。
- 医療機器をMS法人が保有し、医療法人へリース
- 医院用の建物をMS法人が所有し、家賃を設定して貸し出す
- 将来の事業承継を見据えた資産管理会社として運用する
こうした活動は医療法人単体では実行できないため、資産形成や財産管理の視点からMS法人を併用するケースが増えています。
H3:柔軟な人事運用が可能
医療法人では理事や理事長の報酬に上限が設けられていたり、役員報酬の設定や支給方法に制約があります。
一方でMS法人では、家族を役員や従業員として雇用することも可能であり、報酬設計の自由度が高いというメリットがあります。
- 配偶者や子どもを正社員として雇用
- 適正な業務があれば役員報酬を支払う
- 年金や社会保険加入の調整も柔軟に対応できる
このように、収入分散・社会保険対策・事業承継準備など多方面に応用できるのがMS法人の強みです。
H2:MS法人のデメリットと注意点
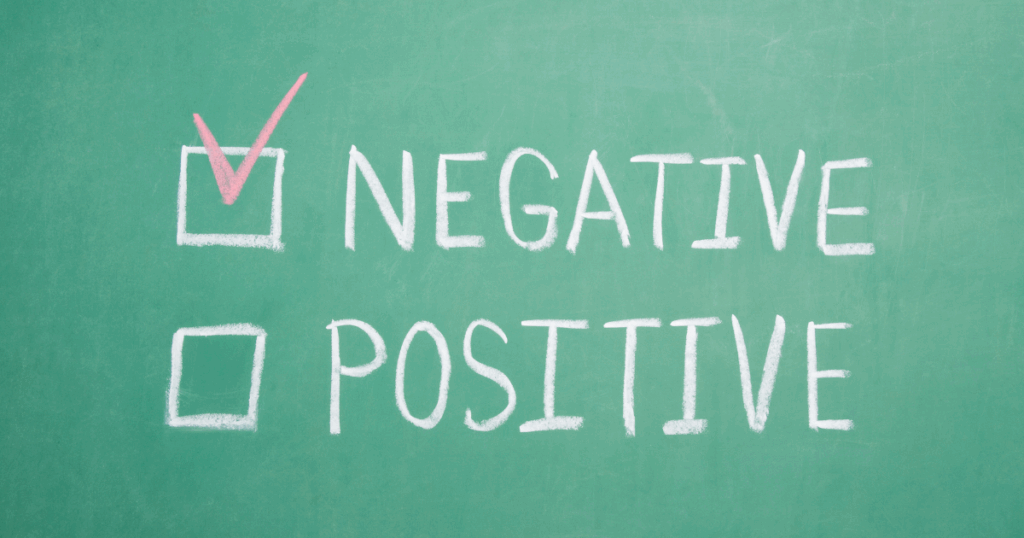
MS法人には節税や資産管理の面で多くのメリットがありますが、使い方を誤ると税務・法務上のリスクを伴う点も無視できません。
とくに医療法人や個人医院との不透明な関係性や、不適切な利益操作は、違法性を疑われる原因になります。
- 過度な節税は違法と判断されるリスクがある
- 利益移転・名義貸しとみなされる可能性
- 運営には法務・会計知識が不可欠
ここでは、MS法人を活用する際に押さえておくべき主なリスクと注意点を解説します。
H3:過度な節税は違法と判断されるリスクがある
MS法人は医療機関と別法人であるため、外注費や賃料などを使って医業所得を圧縮することが可能ですが、それが「実体のない節税スキーム」と見なされた場合、税務署から否認されるリスクがあります。
たとえば次のようなものがあります。
- 業務実態のない家族への高額役員報酬
- 実際には使用していない機器への高額リース料
- 市場価格を無視した不動産賃貸料
これらは、経費ではなく「仮装隠蔽」と判断され、追徴課税の対象になるおそれがあります。節税効果ばかりを狙い、実体の伴わない法人設立はかえってリスクになるので注意が必要です。
H3:利益移転・名義貸しとみなされる可能性
医療法人や個人開業医院からMS法人への過剰な利益移転があると、税務上の「名義貸し」や「利益供与」とみなされるリスクがあります。
これは脱法行為と見なされ、行政処分や課税処分の対象となる可能性があります。たとえば次のようなものがあります。
- 医療法人の理事長がMS法人の代表も兼ねており、両者間の契約内容が曖昧
- 医療法人からMS法人への業務委託が、実際には必要性のない内容で高額設定されている
- 実質的に一体運営されているが、名義上だけ法人を分けている状態
こうした構図は、第三者(税務署や監査機関)から見て正当性を説明できるよう契約書・実績資料を整備しておく必要があります。
H3:運営には法務・会計知識が不可欠
MS法人の設立・運営には、医療法・会社法・税法・労働法など複数の制度の知識が絡みます。医師が自力で運営しようとすると、法的・税務的に不備が生じやすく、リスク管理が不十分になりがちです。
具体的には次のことが挙げられます。
- 適正な法人契約・価格設定の交渉
- 税務調査への対応方針の設計
- 社会保険や労務管理の整備
これらを適切に行うためには、税理士・会計士・弁護士など外部専門家の関与が実質的に必須です。「節税したいからとりあえず作る」という考えでは、かえって失敗する可能性が高まります。
H2:個人開業医でもMS法人は活用できる?

MS法人は医療法人と組み合わせて使うイメージがありますが、実は個人開業医でもMS法人を活用することは可能です。
とくに不動産・機器・人件費などの経営資源を切り分けて管理したい場合や、将来的な承継・相続対策を考える場合に効果的です。
個人開業医のMS法人活用事例
個人開業医でも、MS法人を設立して以下のような機能を切り出すことで、経営の柔軟性と安定性を高めることができます。
| 活用方法 | 内容・効果 |
|---|---|
| 不動産所有 | ・クリニックの土地・建物をMS法人名義で所有し、医院に賃貸することで家賃を経費化 ・将来の売却や移転時も、資産管理が法人単位で分離されているとスムーズ |
| 医療機器の購入・リース | ・高額な医療機器をMS法人が購入 ・保有し、医院にリースする・購入負担の分散と費用処理の明確化が可能 |
| 人件費の処理 | ・受付、事務、清掃など医療行為に関わらないスタッフをMS法人で雇用 ・医院の人件費管理が簡素化され、労務トラブルへの備えにもなる |
さらに、MS法人は将来的に事業承継や相続のスキームにも応用できます。
- 親が医院を経営、子がMS法人を担当して経営を学ぶ
- 不動産や資産をMS法人に移し、医院は事業継続、資産は段階的に承継する
こうした構成は、税負担を抑えつつ、事業の継続性も確保できるため、中長期的な経営戦略の一部としても有効です。
個人開業医でもMS法人の活用余地は十分にあり、「小規模だから不要」と切り捨てるのではなく、長期的視点での検討が価値を生みます。
H2:医療法人とMS法人を兼務することは可能?
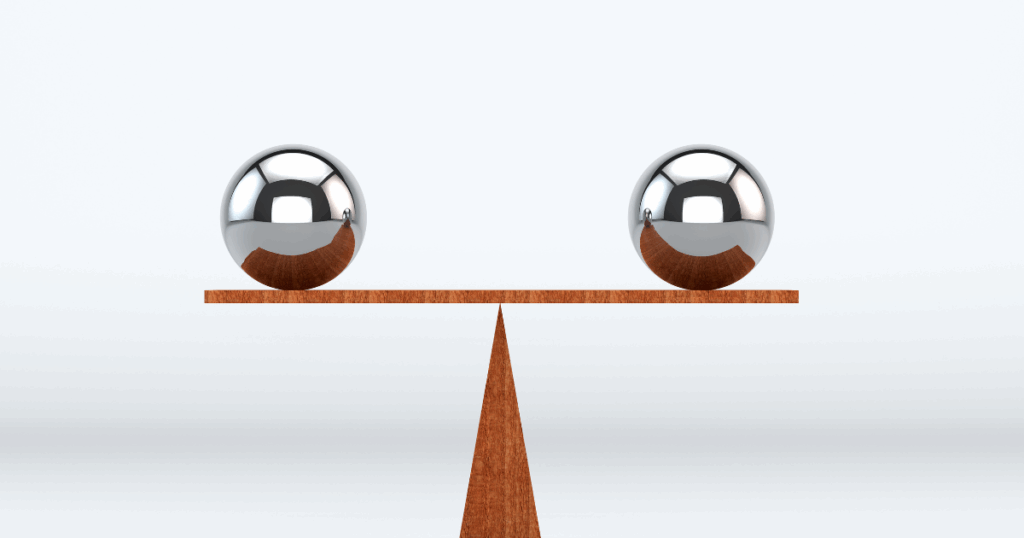
医療法人とMS法人を連携させて運用する際、「理事長や代表が両方の法人を兼務できるのか?」という疑問は多くあります。
結論として、医療法人とMS法人の兼務は法的に可能です。ただし、利益相反が発生しやすいため、透明性のある運用が強く求められます。
H3:兼務は可能だが、利益相反に配慮が必要
医療法人の理事長が、MS法人の代表取締役を兼ねることは制度上、禁止されていません。
実際、多くの開業医が「診療は医療法人」「不動産管理やスタッフ雇用はMS法人」という構成で、両法人の代表を兼務している事例があります。しかしこの場合、特に注意が必要なのが利益相反です。
次のような問題があると、税務調査で「私的流用」「不正な利益移転」として指摘されるリスクがあります。
- 役員報酬や取引内容が医療法人のガバナンスに反していないか
- 医療法人からMS法人への賃料・業務委託料が適正か
- 医療法人の資産がMS法人に不当に流れていないか
そのため、兼務を行う場合には以下のような対策が必須です。これらを徹底することで、法的リスクや税務否認を避けつつ、効率的な法人運営が可能になります。
- 両法人間の契約書を正式に作成し、適正な価格で明示
- 業務実態を証明できる記録(業務報告書・請求書など)を残す
- 必要に応じて、第三者(税理士・行政書士など)による確認体制を設ける
H2:MS法人を活用する際に気をつけたいこと

MS法人は適切に使えば経営効率や節税に役立ちますが、形式だけ整えて実態のない運用をすると、税務署から否認されるリスクが高まります。
とくに節税目的での乱用は、追徴課税やペナルティにつながるおそれもあるため注意が必要です。以下に、MS法人を活用する際に必ず意識すべき重要なポイントを解説します。
H3:節税だけを目的にするとリスクが高い
MS法人を設立する動機として「節税」が挙げられることは多いですが、それだけを目的にすると、制度の本来の趣旨から外れ、税務上のリスクが急上昇します。
たとえば、業務実態のない高額な外注費や家族への名目報酬など、税務署から見て「明らかに利益操作」と判断される構造は、高確率で否認対象となります。
MS法人は本来、医療提供を支援する業務(事務・不動産管理・人材雇用など)を適正に担う法人です。その目的から逸脱した使い方は、かえって損失や信用毀損につながりかねないので注意してください。
H3:実態が伴っていないと税務上否認される可能性あり
MS法人を利用した取引が、書類上だけの名ばかり契約だった場合、税務署はその取引を「なかったもの」として否認します。
- 実際に業務を行っていない家族に対する役員報酬
- 使用実態のない機器や建物に対するリース料・家賃
- 経費に見せかけた実質的な所得移転
これらはすべて、業務実態・市場価格・契約内容の整合性を欠いている場合に否認される可能性が高いです。税務署が確認するのは、帳簿ではなく「実際に何をしているか」です。
H3:契約書や取引価格の妥当性を常に説明できる状態に
MS法人と医療法人(あるいは個人開業医)との取引においては、契約書の存在とその内容の妥当性が非常に重要です。
- 契約の目的と業務範囲が明記されているか
- 対価の金額が市場相場に照らして合理的か
- 業務日報・請求書・振込記録などが残されているか
これらをしっかり整備・保管しておくことで、税務調査や金融機関からの信用調査においても正当性を主張できます。
「後から説明できるか」を基準に書類・運用を組み立てておくことが、長期的にMS法人を安定運用する鍵になります。
H2:まとめ|医療法人とMS法人の違いを理解し、適切に使い分ける
MS法人と医療法人は、目的・業務範囲・法的性質が明確に異なる法人形態です。医療法人は診療を行うための主体であり、MS法人はその経営・事務・資産管理などを担う裏方の法人です。
MS法人を活用することで、節税・資産保有・人事の柔軟性など、医療法人や個人開業医では難しい経営戦略が実行可能になります。
一方で、業務実態のない節税スキームや、医療行為との線引きを誤った運用は、法的・税務的なリスクを高めるだけです。
だからこそ重要なのは
- 両法人の役割を正しく理解すること
- 取引の実態と契約の整合性を保つこと
- 専門家と連携し、透明性を確保しながら運営すること
開業医にとってMS法人は、正しく使えば経営の武器になります。制度の本質を理解した上で、自院の目的や規模に合ったかたちで活用していくことが、将来の経営安定・承継準備にもつながります。