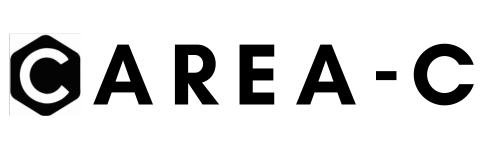歯並びや噛み合わせを整える歯列矯正は、多くの場合で高額な治療費がかかる自由診療です。「保険は使えないの?」「どういうケースなら適用されるの?」と疑問に感じたことがある人も多いはず。
矯正治療でも一部の条件を満たせば健康保険が適用されるケースがあります。ただし、対象となるのは限られた疾患や症例のみで、保険が使える医療機関や手続きにも一定のルールがあります。
この記事では、歯列矯正で保険が適用される具体的な条件や費用、必要な手順、注意点までをわかりやすく解説します。
自分や家族の矯正治療に保険が使えるか気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。
矯正は基本的に自由診療(保険適用外)

歯列矯正は、基本的に「自由診療(保険適用外)」とされています。その理由は、保険診療が原則として「病気やケガの治療を目的とする医療行為」に限定されているからです。
矯正治療の多くは、審美目的や軽度の噛み合わせの改善などが主な目的とされることが多く、これが「治療」ではなく「見た目や快適さの向上」に分類されるため、保険適用外という扱いになります。
たとえば、歯並びをきれいにしたい、前歯の隙間が気になる、出っ歯を治したい――こういった理由での矯正は、機能的な障害が明確でない限りは、保険が使えないのが一般的です。
とはいえ、制度上の区分としては、「見た目や快適さを重視した医療」は原則自由診療扱いです。そのため、費用は全額自己負担となり、数十万円〜百万円以上かかることもあります。
ただし、すべての矯正治療が保険適用外というわけではありません。機能的な障害がある場合や、特定の疾患に該当するケースでは、例外的に保険が使える場合があります。
では、どのような条件を満たせば保険が適用されるのでしょうか?次に、保険適用の条件について詳しく解説します。
歯科矯正が保険適用になる条件とは?

保険が適用される矯正治療は、以下のような医学的に機能障害が認められるケースに限定されています。
- 疾患に起因した咬合異常(厚生労働省が定めた指定疾患)
- 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常
- 顎変形症の手術前後
たとえば、咀嚼(そしゃく)や発音などに明らかな支障がある顎の異常や、先天的に口腔や骨格に問題がある場合、「医療としての矯正治療」として保険適用が認められることがあります。
また、矯正治療が保険適用されるためには、「指定自立支援医療機関(育成・更生医療)」または「顎口腔機能診断施設」に認定された医療機関で治療を受けること」が絶対条件です。
保険が使える矯正治療には、年齢制限はありません。子どもでは成長期におこなう矯正治療が適用対象になることも多く、大人は原則自由診療ですが、医学的理由があれば保険対象になるケースもあります。
①歯科矯正の保険適用になる指定疾患について
厚生労働省が保険適用対象と定めている疾患は、令和7年現在、約65種類あります。
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
- 鎖骨頭蓋異形成症
- トリーチャ・コリンズ症候群
- ピエール・ロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセル・シルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ウイーデマン症候群
- 顔面半側萎縮症
- 先天性ミオパチー
- 筋ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 顔面半側肥大
- エリス・ヴァンクレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダー・ウィリー症候群
- 顔面裂(横顔裂、斜顔裂および正中顔裂を含む)
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口腔・顔面・指趾症候群
- メビウス症候群
- 歌舞伎症候群
- クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
- ウイリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群および尖頭合指症を含む)
- 骨形成不全症
- フリーマン・シェルドン症候群
- ルビンスタイン・ティビ症候群
- 染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分無歯症
- CHARGE症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群およびXXXXX症候群を含む)
- リング18症候群
- リンパ管腫
- 全前脳胞症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
- 線維性骨異形成症
- スタージ・ウェーバー症候群
- ケルビズム
- 偽性副甲状腺機能低下症
- Ekman-Westborg-Julin症候群
- 常染色体重複症候群
- 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
- 毛髪・鼻・指節症候群(Tricho-Rhino-Phalangeal症候群)
- クリッペル・ファイル症候群(先天性頸椎癒合症)
- アラジール症候群
- 高IgE症候群
- エーラス・ダンロス症候群
- ガードナー症候群(家族性大腸ポリポージス)
- その他顎・口腔の先天異常(※)
※その他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度厚生局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
これらの疾患に該当する患者が、咀嚼障害や発音障害などの症状を伴う場合、医師の診断を経て保険適用での矯正治療が認められます。
対象疾患は厚労省の通知で随時更新されることがあるため、最新情報は厚労省の資料や大学病院等で確認するのが確実です。
②前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常について
通常、永久歯は6歳頃から生え始め、12歳前後で生え揃います。しかし、永久歯が3本以上生えてこない状態が続く場合、「永久歯萌出不全(えいきゅうしほうしゅつふぜん)」と診断されることがあります。
これは、先天的に歯が存在しない場合や、歯ぐきの中に埋まっていて自然に出てこない場合(埋伏歯)などが原因で、噛み合わせ(咬合)に支障が出ている状態です。
永久歯萌出不全による矯正治療で保険が使えるのは、以下の場合に限られます。
| 永久歯の状態 | 咬合異常あり | 埋伏歯開窓術の診断 | 指定医療機関での診断 | 保険適用 |
|---|---|---|---|---|
| 3本以上の永久歯が萌出していない | あり | 必要 | 受けている | 保険適用 |
| 3本以上の永久歯が萌出していない | あり | 不要 | 不問 | 自由診療 |
| 1〜2本の永久歯が萌出していない | なし | 不問 | 不問 | 自由診療 |
このように、補填適用になるのは、3本以上の永久歯が萌出しておらず、咬合異常がある。また指定医療機関で埋伏歯開窓術が必要だと診断されている場合に限ります。
埋伏歯開窓術とは、歯ぐきの中に埋まって生えてこない歯(埋伏歯)を露出させるために、歯ぐきを切開する手術のこと。
③顎変形症の手術前後について
顎変形症(がくへんけいしょう)とは、上下の顎の骨の位置や形に異常があり、噛み合わせや顔貌(外見)に影響を与える状態のことです。代表的な例は以下のようになります。
- 下顎が前に出る(反対咬合・受け口)
- 上顎が前に出すぎている(出っ歯)
- 顎が左右にずれている(顔面非対称)
これらは、単に歯並びの問題ではなく、骨格レベルでの異常とされ、医科と歯科の連携による「外科的矯正治療(サージェリーファースト含む)」が必要になることがあります。
また、顎変形症と診断されても、診断基準に達していない軽度のケースでは保険が適用されないこともあるため、判断は専門機関に委ねる必要があります。
保険が適用された場合の費用と内容

矯正治療が保険適用になると、自由診療に比べて大幅に費用を抑えることが可能です。ただし、適用されるのは「医学的に必要なケース」に限られ、対象となる診療内容や機関も指定されています。
ここでは、保険が適用された場合の自己負担額や、どこまでが保険対象になるのかについて詳しく説明します。
自己負担は基本3割
保険が適用された場合、自己負担の割合は一般的な医療と同じルールが適用されます。
- 70歳未満の大人:原則3割負担
- 就学前の乳幼児〜高校生相当の子ども:1〜2割負担(自治体によって差あり)
- 高齢者(70歳以上):所得に応じて1〜3割負担
たとえば、自由診療で100万円程度かかる全体矯正が、保険適用により数十万円程度の実費に収まることもあります。
また、子どもに関しては、地域の乳幼児医療制度や子ども医療費助成が使える場合があり、実質負担ゼロ〜数千円になるケースも存在します。
保険適用の対象に含まれる
保険が適用された場合、以下のような治療内容が対象になります。
- 初診・精密検査(レントゲン、口腔模型、顎の診断等)
- 矯正装置の装着・調整
- 治療中の通院費用
- 経過観察・保定装置(リテーナー)など
つまり、矯正に必要なプロセス全体が一貫して保険対象になるのが特徴です。
ただし、装置の種類には制限があります。自由診療では見た目に配慮した透明なマウスピース矯正や裏側矯正(舌側矯正)なども選べますが、保険診療では原則として「機能回復を目的としたワイヤー矯正」が中心です。
また、治療の中で抜歯や外科手術が必要になった場合も、保険適用の範囲内で対応されます。
保険が使えない場合の費用と対策

保険が適用されない矯正治療は、すべて自由診療(全額自己負担)となります。特に成人矯正や審美目的の矯正では、保険が使えないのが一般的です。
費用が高額になりやすいため、「いくらかかるのか」「支払い方法に選択肢はあるのか」など、事前に知っておくことが重要です。
自由診療の費用相場
矯正治療の自由診療費用は、使用する装置や治療範囲によって異なりますが、全体矯正の場合は80万〜120万円程度が相場です。
| 治療内容 | おおよその費用(目安) |
|---|---|
| 表側矯正(ワイヤー) | 80万〜100万円程度 |
| マウスピース矯正 | 90万〜120万円程度 |
| 部分矯正(前歯のみ等) | 20万〜60万円程度 |
また、初診料・検査料・調整料・保定装置(リテーナー)などが別途かかるケースもあり、総額では+10万〜20万円程度になることもあります。
歯科医院によって料金体系が異なるため、事前の見積もり確認と比較が必須です。
医療費控除の対象になる?
自由診療の矯正治療でも「医療費控除」の対象になる場合があります。対象になるのは、以下の条件を満たすときです。
- 咀嚼(そしゃく)や発音などの機能回復が目的の治療であること
- 子どもの成長に伴う不正咬合の予防・改善を目的とする場合
逆に、「見た目をよくしたい」「美容目的」と判断される場合は、医療費控除の対象外となります。
控除を受けるには、治療費の領収書を保管し、確定申告で申告する必要があります。
また、支払額が年間10万円を超えた場合、超過分が控除の対象になります。
デンタルローンや分割払いなどの現実的な支払い方法
矯正治療は高額なため、一括で支払うのが難しいという人も少なくありません。多くの歯科医院では、以下のような分割払いの選択肢を用意しているので、利用を検討してみましょう。
支払い方法の例
| 支払い方法 | 特徴 |
|---|---|
| デンタルローン | 専用の医療ローン。月々数千円〜数万円で支払える。信販会社を通じて審査が必要。 |
| 院内分割払い | 歯科医院が独自に設定。手数料無料または少額で利用できることもある。柔軟な対応が多い。 |
| クレジットカード分割 | ポイントが貯まるが、金利が高め。利用上限に注意が必要。 |
無理のない計画を立てるためにも、初診時に支払い方法について相談し、納得できるプランを選ぶことが重要です。
歯科矯正に保険適用させる手順

保険適用で矯正治療を受けたい場合、まず重要なのは「自分が保険適用の条件に該当しているかどうか」を正しく診断してもらうことです。
対象となる疾患や状態は限られており、通常の歯科医院では診断や手続きができないケースもあるため、正しい流れで進める必要があります。
まずは保険適用対象かどうかを診断できる歯科を受診する
矯正治療と保険診療に詳しい歯科医院で相談・初診を受けることです。この時点で、「噛み合わせや顎の状態に医学的な異常があるか」「先天性疾患などに該当するか」などを見極めてもらう必要があります。
ただし、保険が適用されるかどうかは一般の矯正歯科では判断できないこともあるため、「必要があれば専門機関を紹介してくれる歯科かどうか」も選ぶポイントです。
大学病院や「保険適用矯正の指定医療機関」での相談が必要
保険適用の矯正治療を受けるためには、厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生(支)局に届け出がされている保険医療機関での診断と治療が必要です。
これらの医療機関は、大学病院や総合病院の歯科・口腔外科に多く存在していますが、すべての歯科医院が対象というわけではありません。
実際に保険が使えるかどうか確認したい場合は、地方厚生(支)局の公式サイトで「指定医療機関」の一覧を検索できるようになっています。検索方法はつぎのとおりです。
- 厚生労働省の「地方厚生(支)局」ポータルにアクセス
- お住まいの地域に該当する地方厚生(支)局のページを選択
- サイト内検索で「施設基準届出受理医療機関名簿」と入力
- 表示されたページから、都道府県別の一覧にある「歯科」のPDFを開く
- PDF内で『矯診』『顎診』の表記を探す
| 表記 | 意味 |
|---|---|
| 矯診 | 先天性疾患や永久歯が3本以上生えてこないなど |
| 顎診 | 顎の手術をともなう矯正治療(顎変形症など) |
- リストはPDF形式なので、「Ctrl+F(検索)」で「矯診」「顎診」と入力すれば見つけやすくなります。
- 名簿は定期的に更新されるため、最新のものを確認してください。
セカンドオピニオンも視野に入れて確認する
診断結果が「保険適用外」とされた場合でも、セカンドオピニオンを求めるのは有効です。
顎変形症や咬合異常の診断は、診療機関や医師によって判断に差が出ることもあります。「適用外と言われたけど納得できない」「他でも見てもらいたい」と感じたら、他の指定医療機関や大学病院に相談してみることで、異なる見解が得られる可能性もあります。
特に高額な治療になる矯正では、診断・方針に納得してから治療を始めることが、結果的に安心と満足度につながります。
まとめ
歯列矯正は、基本的に保険が適用されない自由診療ですが、一部の疾患や顎の異常が認められる場合に限って、保険で治療できるケースがあります。
保険が適用される主なケースは以下のとおりです。
- 先天性疾患(例:口唇裂、ダウン症など)に伴う咬合異常
- 永久歯の萌出不全(3本以上)により咬合異常がある場合で、外科的処置を伴うもの
- 顎変形症で外科的矯正手術が必要なケース
いずれの場合も、「厚生労働省に届け出済みの指定医療機関(矯診・顎診)」で診断と治療を受けることが条件です。
保険が使えない場合は、治療費が全額自己負担となり、全体矯正で80万〜120万円程度が目安となります。ただし、医療費控除や分割払い(デンタルローン)などの選択肢もあります。
矯正治療を検討するなら、まずは以下を確認しましょう。
- 自分の症例が保険適用の対象になるか
- 指定医療機関で診断を受ける方法
- 保険適用外の場合に備えて、費用や支払い方法を事前に把握しておくこと
制度はやや複雑ですが、正しい知識と手順を押さえておけば、無駄な費用や時間を避けることができます。
将来の口元と健康のために、「保険が使える可能性があるかどうか」を一度しっかり確認しておくことをおすすめします。