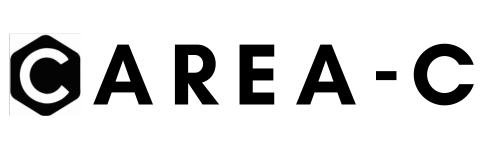「なんとなく体がだるい…」そんな不調、見逃していませんか?
疲れやすい、寒がり、むくみ、肌の乾燥、気分の落ち込み。こうした一見ありふれた不調が、実は「甲状腺機能低下症」のサインかもしれません。
甲状腺ホルモンが不足すると、全身の代謝が落ちてさまざまな症状が現れますが、自覚しにくく、放置されやすいのが特徴です。
この記事では、甲状腺機能低下症の代表的な症状やチェック方法、検査・治療の流れ、注意すべき食事内容までをわかりやすく解説します。
甲状腺機能低下症とは?|橋本病との違いも含めて解説

「なんとなく体がだるい」「気分が落ち込みやすい」「寒がりになった」——これらの不調、甲状腺機能の低下が原因かもしれません。
甲状腺機能低下症は、体の代謝を調整する甲状腺ホルモンが不足することで、全身にさまざまな症状を引き起こす病気です。
中でもよく耳にする「橋本病」との関係は混同されやすく、正確な理解が求められます。ここでは、甲状腺の役割や体への影響、そして橋本病との違いについて詳しく解説します。
甲状腺の働きと体への影響
甲状腺は、のどぼとけの下あたりに位置する小さな臓器で、体にとって重要なホルモンを分泌しています。
具体的には、「甲状腺ホルモン(T3・T4)」と呼ばれるホルモンを作り、全身の代謝や体温、心拍、消化機能、精神状態などを調整しています。
このホルモンが不足すると、エネルギーの消費が落ち、体のあらゆる機能が低下します。結果として、疲れやすさ、寒がり、むくみ、皮膚の乾燥、便秘、気分の落ち込みなどが現れやすくなります。
つまり、甲状腺ホルモンの分泌量は、体のエンジンを動かす出力に関わる重要な要素と言えます。
甲状腺機能が正常に働いていれば、こうした機能はバランスよく保たれますが、ホルモンが不足するとさまざまな不調を引き起こすことになります。
甲状腺機能低下症と橋本病の違い
甲状腺機能低下症とは、甲状腺ホルモンの分泌が不足している状態を指します。
一方、橋本病は、その原因のひとつです。橋本病は自己免疫疾患の一種で、免疫の異常により自分の甲状腺を攻撃して炎症を起こし、徐々に機能を低下させていきます。
つまり、橋本病は甲状腺機能低下症を引き起こす「原因疾患」のひとつという位置づけです。実際、日本人女性に多く見られる甲状腺機能低下症の主な原因は橋本病です。
ただし、甲状腺機能低下症の原因は橋本病だけではありません。たとえば、甲状腺の手術後、放射線治療の影響、あるいは一部の薬剤の副作用によっても機能低下が生じることがあります。
混同されがちですが、「橋本病=甲状腺機能低下症」ではなく、橋本病によって甲状腺ホルモンが出にくくなることで、甲状腺機能低下症になるという因果関係があります。
橋本病は初期では無症状のこともあり、気づかずに進行するケースもあるため、正確な診断が重要です。
甲状腺機能低下症の症状とは?|部位別・特徴別に解説

甲状腺機能低下症は全身に影響を与える病気であり、その症状は多岐にわたります。特定の部位だけに出るのではなく、代謝全体が落ちることで、さまざまな臓器や機能に不調が現れます。
症状が曖昧なことも多く、見逃されがちです。ここでは、代表的な症状、首の腫れとの関係、さらに放置した場合の進行リスクまで、具体的に解説します。
代表的な症状チェック|疲れ・寒がり・むくみなど
甲状腺ホルモンが不足すると、エネルギーの産生が低下し、体の活動全般が鈍くなります。結果として、以下のような症状が現れます。
| 症状 | 説明 |
|---|---|
| 慢性的な疲労感 | 寝ても取れないだるさ、体が重い感覚が続く |
| 寒がり | 冷え性とは異なり、室内でも寒さを強く感じやすい |
| むくみ | 特に顔やまぶたがむくみやすく、朝に強く出る傾向 |
| 皮膚の乾燥・かゆみ | 代謝の低下によって皮膚が乾燥しやすくなる |
| 体重増加 | 食事量が変わらないのに太る |
| 便秘 | 腸の動きが鈍くなるため、排便回数が減る |
| 抑うつ気分・集中力低下 | 気分の落ち込みや記憶力の低下も起こりやすい |
これらの症状は、日常的な不調や加齢と誤解されることが多く、診断が遅れがちです。複数が重なっている場合は、一度甲状腺の検査を受けることを推奨します。
甲状腺機能低下症と首の腫れ|「甲状腺が腫れる」とはどういう状態か?
甲状腺機能低下症では、首の前面にある「甲状腺」が腫れてくることがあります。特に橋本病が原因の場合、慢性的な炎症が起きており、それに伴って甲状腺が肥大する(=びまん性甲状腺腫)ことがあります。
この腫れは痛みを伴わないのが特徴で、鏡を見たときや触ったときに気づくケースが多いです。初期では見た目に大きな変化はないこともありますが、進行すると喉の圧迫感や飲み込みづらさを感じることもあります。
ただし、「腫れている=必ず機能低下がある」とは限らず、正常なホルモン値を保っているケースもあるため、首の腫れに気づいた場合は自己判断せず、医療機関でホルモン検査を受けることが重要です。
甲状腺機能低下症を放っておくとどうなる?
甲状腺機能低下症を放置すると、症状はゆっくりと進行します。長期間ホルモン不足の状態が続くと、以下のような重篤な合併症を引き起こすことがあります。
| 症状・合併症 | 説明 |
|---|---|
| 心拍数の低下・心不全リスク | 心臓の働きが低下し、不整脈や心不全の原因になる |
| 意識障害(粘液水腫性昏睡) | 極端なホルモン不足により、意識レベルが低下する重篤な状態。高齢者や冬場に起こりやすい |
| 高コレステロール血症 | 代謝が落ち、LDLコレステロールが増加する |
| 不妊・月経異常 | ホルモンバランスが崩れ、女性の生殖機能に影響 |
また、精神的な症状が強くなると、うつ病と誤診されることもあります。
こうした進行を防ぐには、早期の検査・治療が不可欠です。放置すれば自然に治るものではなく、放っておくと生活の質を大きく損なう可能性があります。
甲状腺機能低下症 症状チェック|セルフチェックと受診の目安
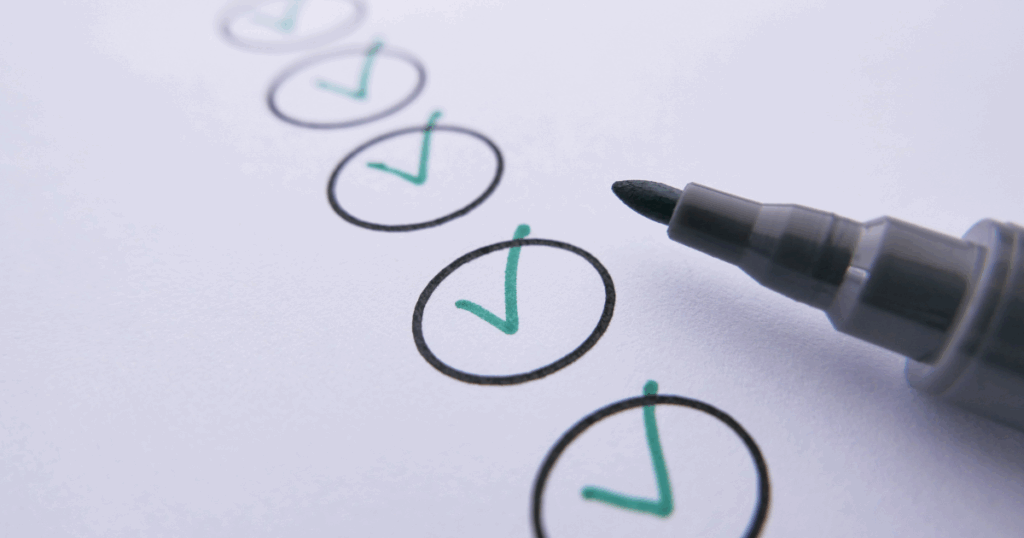
甲状腺機能低下症は症状が曖昧なため、見逃されやすい病気です。
体調の変化が気になる場合、まずはセルフチェックで傾向を確認することが大切です。ただし、自己判断はあくまで参考に留め、気になる症状があれば早めの受診を検討しましょう。
ここでは、自宅で確認できる症状チェックリストと、受診先やタイミングについて解説します。
セルフでできる症状チェックリスト
以下のチェックリストは、甲状腺ホルモンの不足によって起こりやすい症状をもとにしています。3項目以上当てはまる場合は、甲状腺機能低下の可能性を考慮して医療機関に相談をおすすめします。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| □ 疲れやすい | 睡眠を取っても疲労感が取れない |
| □ 寒がりになった | 暖かい場所でも寒さを感じやすい |
| □ 顔やまぶたがむくむ | 特に朝起きたときにむくみが目立つ |
| □ 肌が乾燥しやすくなった | 以前より肌がカサつく、粉をふく |
| □ 体重が増えた | 食事量が変わっていないのに太った |
| □ 便秘気味 | 排便回数が減った、スッキリしない感覚がある |
| □ 気分が落ち込む | 理由もなく不安感や抑うつ状態が続く |
| □ 記憶力や集中力が落ちた | 会話や作業中に思考が止まりやすい |
| □ 月経が不規則になった | 女性の場合、生理周期の乱れや量の変化がある |
| □ 首の前が腫れてきた | のどぼとけの下あたりが膨らんできた気がする |
このチェックリストは診断を確定するものではありません。「年齢のせい」「ストレスのせい」と見過ごされがちな体調変化も、甲状腺機能が関係していることがあります。
どの診療科に行けばいい?受診タイミングの見極め方
甲状腺の症状が疑われる場合、受診先としては内分泌内科または一般内科が適しています。
甲状腺専門の外来がある病院もありますが、まずは地域の内科で血液検査(TSH・FT3・FT4)を受けるだけでも判断材料になります。
以下のような場合は、特に受診を検討してください。
- チェックリストの該当項目が3つ以上ある
- 2週間以上にわたり、体調不良が改善しない
- 首の腫れや違和感を感じている
- 他の原因(睡眠不足・生活習慣など)では説明がつかない不調が続いている
症状が軽度でも、放置すると進行しやすい病気です。早期の診断と治療で、日常生活の質を大きく維持することが可能なため、迷ったら早めの相談を心がけましょう。
甲状腺機能低下症の検査

甲状腺機能低下症は、症状だけで判断するのが難しいため、正確な診断には血液検査が欠かせません。
見た目や自覚症状だけでは他の病気と区別しづらいため、検査を受けてホルモンの値を数値で確認することが重要です。ここでは、実際に行われる検査の内容と、検査前に知っておくべき注意点について解説します。
血液検査(TSH・FT4)
甲状腺機能低下症の診断では、主に以下の2つのホルモン値を血液検査で測定します。通常、TSHが高く、FT4が低いという組み合わせであれば、典型的な甲状腺機能低下症と判断されます。
| 検査項目 | 内容・意義 |
|---|---|
| TSH(甲状腺刺激ホルモン) | 脳(下垂体)から分泌され、甲状腺に「ホルモンを出すように」と指示を出すホルモン。甲状腺機能が低下すると、これが高くなる傾向がある。 |
| FT4(遊離サイロキシン) | 甲状腺から分泌されるホルモンの一種。体の代謝を調整する。甲状腺機能低下症ではこの値が低下する。 |
この2つの数値を見ることで、甲状腺そのものの働きだけでなく、脳からの指令が正常に出ているかどうかも分かります。
必要に応じて、抗TPO抗体や抗サイログロブリン抗体といった自己抗体検査を追加することもあり、これにより橋本病かどうかの判断材料にもなります。
検査を受けるときの注意点
検査に特別な準備は不要ですが、以下の点には注意してください。
- 空腹である必要はないが、医療機関の指示に従う
- サプリやヨウ素を含む健康食品は、事前に医師に申告する
- 他の病気で治療中の場合は、服薬内容を伝える
検査結果が出るまでには通常数日程度かかります。数値に異常が見つかった場合は、必要に応じて精密検査や治療方針の相談が行われます。
甲状腺機能低下症は治る?
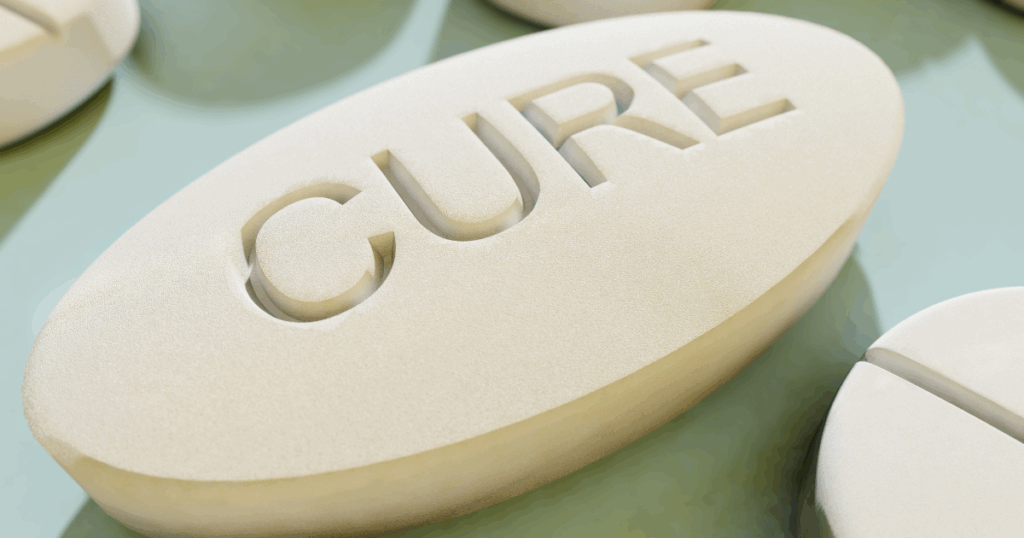
「この病気は一生治らないのか?」「薬はずっと飲み続けるのか?」——甲状腺機能低下症と診断された人の多くが抱く疑問です。
ここでは、治療の実際やQOL(生活の質)への影響、自然に治る可能性があるパターンについて詳しく解説します。
甲状腺機能低下症は自然に治る?|治療期間と完治について
甲状腺機能低下症が自然に治るかどうかは、「原因によって異なる」のが結論です。
一時的な甲状腺炎(例:出産後甲状腺炎やウイルス感染など)が原因の場合、時間の経過とともに甲状腺の機能が回復し、薬が不要になることもあります。このようなケースでは、治療期間は数ヶ月から1年以内に収まることが多く、再発も少ないとされています。
一方、橋本病のような自己免疫性疾患が原因の場合、甲状腺の細胞が慢性的に破壊されるため、自然に治ることはほぼありません。この場合は、不足したホルモンを一生にわたり補充する治療(ホルモン補充療法)が基本となります。
ただし、長期治療が必要でも、ホルモン量が安定すれば日常生活は支障なく送れるようになります。治療を続けているからといって「ずっと体調が悪い」「生活が制限される」といったものではありません。
重要なのは、自分の甲状腺機能低下症が一時的か慢性かを明確にし、それに合った治療方針を知ること。早期に医師の診断を受けることで、無駄な不安を減らし、体調を正しくコントロールしていくことができます。
甲状腺機能低下症の人が避けるべき食べ物とは?

特に注意したいのが「ヨウ素」の摂取量です。
甲状腺ホルモンの材料である一方で、過剰に摂取すると、かえってホルモンの分泌や治療効果に悪影響を与える場合があります。
ここでは、医療機関でも明確に指導されている「ヨウ素制限」について、根拠と具体的な食品例を交えて解説します。
ヨウ素の過剰摂取に注意すべき理由
ヨウ素は、甲状腺ホルモン(T3・T4)の構成要素であり、人体に不可欠なミネラルです。
ただし、甲状腺機能低下症の患者、とくに橋本病などの慢性甲状腺炎がある場合は、ヨウ素の過剰摂取が症状の悪化や治療効果の妨げにつながることがあります。
過剰なヨウ素は、一時的に甲状腺ホルモンの合成を抑制する「ウルフ-チャイコフ効果」などの作用を通じて、甲状腺機能をさらに低下させるおそれがあるため、医師の管理下で摂取量を調整することが推奨されています。
ヨウ素を多く含む食品一覧【摂りすぎ注意】
ヨウ素はさまざまな食品に含まれていますが、特に海藻類に非常に多く含まれています。日本の食文化では昆布やわかめを日常的に使うため、無意識にヨウ素を摂りすぎているケースもあります。
甲状腺機能低下症と診断された場合、ヨウ素の摂取量は医師の管理下で調整すべき重要なポイントです。以下は、特に注意したい食品の一覧です。
| 食品分類 | 食品例 | 備考 |
|---|---|---|
| 海藻類(特に注意) | 昆布、ひじき、わかめ、もずく、海苔 | 100gあたりのヨウ素含有量が非常に高い。昆布だしにも含まれるため、摂取量に注意。 |
| 魚介類(中程度) | たら、あさり、いわし、さば、かつお、鮭など | 海藻ほどではないが、継続的な大量摂取は控える。 |
| 加工食品・外食 | 昆布茶、佃煮、つくだ煮入りおにぎり、みそ汁(だしに昆布使用) | 原材料表示を確認。昆布だしや乾燥海藻に注意。 |
| サプリメント・健康食品 | ヨウ素入りマルチビタミン、昆布エキス含有商品 | 医師の許可なしに継続使用しない。含有量不明な商品も避ける。 |
食事管理のポイント|過度な制限ではなく「適量」に
甲状腺機能低下症の食事で大切なのは、「○○は一切食べてはいけない」と極端に考えず、ヨウ素を中心に摂りすぎないことを意識することです。
無理に制限しすぎないために以下のポイントを重視しましょう。
- 海藻類は「ゼロ」にする必要はない
医師から明確に制限されていない場合、週1〜2回程度の少量摂取であれば問題ないことが多いです。昆布だしを使わない日を設けるなど、調整で対応できます。
- 昆布だしや外食の隠れヨウ素に注意
毎日味噌汁や煮物を食べていると、気づかないうちに昆布由来のヨウ素を摂っていることがあります。だしの種類や調味料の表示を確認する習慣をつけましょう。
- サプリ・健康食品のヨウ素入りを避ける
成分量が不明な商品や甲状腺サポートなどをうたう製品には注意が必要です。摂取する前に医師に相談するのが基本です。
- 自己判断での制限・除去はしない
栄養が偏ることで、疲れやすさ・肌荒れなど他の不調を招く可能性があります。気になる食品がある場合は、医師や管理栄養士に相談するのが確実です。
食事は毎日の積み重ねです。甲状腺機能低下症の治療中でも、避けるべき食品を把握し、適量を守ることで健康的な食生活は十分に可能です。不安を感じたときは、早めに医療機関に相談しましょう。
まとめ
甲状腺機能低下症は、早期に気づいて治療を始めれば、日常生活に大きな支障なくコントロール可能な病気です。疲れやすさ、むくみ、寒がりなどの「見過ごされがちな体調の変化」が続く場合は、自己判断せず医療機関での検査を受けることが第一歩です。
治療ではホルモン補充薬の服用が中心となり、継続することで体調は安定します。ただし、自己判断での服薬中断や、サプリ・特定食品の過剰摂取はリスクになることもあるため、医師の指導を守ることが重要です。
また、食事管理ではヨウ素の摂取量に注意しながらも、栄養バランスを保った無理のない食生活を心がけることがポイントです。
体調に不安があるとき、「年齢のせい」「疲れがたまっているだけ」と片付けず、一度、甲状腺の検査を受けてみるという意識が、健康維持につながります。自分の身体のサインを見逃さず、必要なケアを早めに始めましょう。